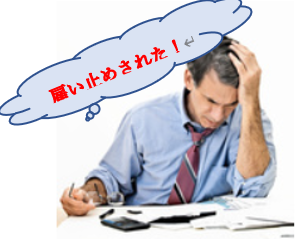運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所
〒224-0007 神奈川県横浜市都筑区荏田南1-19-6-655
うつ病等、精神疾患による申請事例と認定基準
うつ病など「気分障害」患者数が 推定111万人、過去最多に!


うつ病など「気分[感情]障害(躁うつ病含む)」患者数が 、推定111万人(2014年10月時点)、過去最多になりました。
日本では精神疾患を患う患者は、300万人以上!ここ数年で大きく増加しています。
なかでも一番多いのがうつ病で、次に多いのが、統合失調症、不安障害、認知症と続いており、特にうつ病と認知症が近年著しく増加の一途を辿っているのです。
少しでも多くの患者様に、障害年金制度をご理解いただきたいものです。
精神疾患の障害年金認定ポイントは!
障害状態は総合的に認定!
精神疾患による障害状態は、その原因、諸症状、治療、及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。
労働及び日常生活上の制限!
精神疾患の症状は、同一原因であっても多種多様です。
従って、認定にあたっては具体的な労働制限及び日常生活状況等の生活上の制限を判断するとともに、その精神疾患の原因と病状の進捗状況等が判断材料にされます。
厚労省からのお知らせ!

平成28年7月15日に精神障害及び知的障害に係る認定において、ガイドラインが発表されました。
かねてより地域による精神・知的・発達障害の判定の格差において専門家検討会が行われていましたが、厚労省よりガイドラインが発表されました。
精神の障害に係る等級判定ガイドライン

平成28年2月に専門家検討会が行われました。
精神障害及び知的障害に係る認定において、ガイドラインの改善を図る目的で議論されました。
以前より、障害年金の認定基準をめぐっては、精神・知的・発達障害の判定に地域でばらつきがあることが問題になっていました。
様々な問題解消の為、認定基準が大きく改善される予定です。

H28年7月15日付年金局事業管理課長通知より、新しい認定基準のガイドラインが発表され、H28年9月から実施されることになりました。
従来からの下記検討内容や案と殆ど同じです。
検討会の内容は、下記からご確認下さい。
日本年金機構関連資料はこちらを参照
さまざまな症状別に、詳しくご紹介いたします。
「さらに詳しく精神疾患の専門ページ」はこちらです。
ICD10コードとは、死亡や疾病のデータの体系的な記録、分析、解釈及び比較を行うため、世界保健機関憲章に基づき、世界保健機関(WHO)が作成した分類です。
このコード番号が、記入漏れ及び年金支給対象外となっていた場合、本人が知らないうちに不支給になることがあります。
認定される上で非常に重要なコード番号です。
詳しくはこのぺージの「認定要領」をご覧ください。
以下、具体的な「事例」とその「認定ポイント及び基準」についてご紹介させて頂きます。
身体の機能の障害と精神の障害がある方はこちらも!
精神疾患の障害年金申請の事例
障害年金申請事例をご紹介いたします。
躁うつ病の事例
Yさん 男性:44歳
| 病名 | 躁うつ病(双極性感情障害) | ||
| 性別・年齢 | 44歳男性:サラリーマン生活を長年していた。 | ||
|
症状 | ご本人の奥様からの相談です。
| ||
| 請求結果 | 障害厚生年金2級+障害基礎年金2級(遡り4年) | ||
【今回の申請での認定ポイントほつぎのとおりです。】
内科で受診した日が初診日
Yさんの場合、最初に受診したのが内科だった為、内科での受診が初診日になりました。
精神疾患の場合、色々と病院内を転医されることが多く、初診日の確定は難しいのですが、診療科が精神科でなくても、最初に受診した科となります。
日常生活では家族の援助が必要
障害の等級を認定する上で重要な判断材料になります。
診断書における、日常生活の判定では、身辺の清潔保持、金銭の管理、身辺の安全保持及び危機対応の項目の殆どが家族の援助なしでは出来ない事を証明してもらえました。
社会生活にも支障
外出や他人とのコミュニケーションが家族の援助なしでは難しいことも障害の状態を把握するための重要な判断材料になりました。
通常のようには労働できず、就労していなかった
転職を繰り返したが、結局精神的に就労する自信がなくなってしまったこと。
就労出来ないことは、2級に認定されるための重要な判断材料になります。
4年前まで遡り請求が出来た
初診時の病院が大学病院の為、同じ病院内で転医治療し、障害認定日(1年半経過)の診断書の取得が出来た事。(遡り4年)
遡り請求の場合、最初の受給額が遡った月分(この場合年金の4年分)支給されますので、障害者の方にとって非常に助かりました。
以上のポイントが認定材料となり、障害厚生年金2級+障害基礎年金2級を受給。
てんかん の事例
Iさん 女性:23才
病名 | てんかん | ||
| 性別・年齢 | 23歳 女性:アルバイト・家事手伝い | ||
|
症状
|
| ||
| 請求結果 | 障害基礎年金2級(遡り認定) | ||
統合失調感情障害 の事例
Mさん 女性:23歳
| 病名 | 統合失調感情障害 | ||
| 性別・年齢 | 23歳:女性 | ||
| 症状 |
| ||
| 請求結果 | 障害厚生年金2級+障害基礎年金2級(認定日請求) | ||
【今回の申請での認定ポイントほつぎのとおりです。】
最初に受診したクリニックが初診日
最初の病院で初診日証明「受診状況等証明書」が取れたこと。
日常生活で家族の援助が必要
診断書における日常生活の判定項目で適切な食事摂取、金銭の管理と買い物が家族の援助なしではできないこと等を証明して頂いたこと。
社会生活に支障
外出や他者とのコミュニケーション、公共施設の利用等家族の援助なしでは出来ないこと。
今後、治る見込みが余りない
今後も、同様の症状が継続されることが予想されること。
精神疾患の障害等級認定基準
■ 精神疾患の障害については、次のとおりです。
| 障害の程度 | 障害の状態 |
1 級 | 精神の障害であって、日常生活がおおむねベッドでの生活であること これと同程度以上と認められる程度のもの |
| 2 級 | 精神の障害であって、日常生活は一部家族の援助なしでは出来なく、おおむね家屋内にいる状態。又はこれと同程度以上と認められる程度のもの |
|
3 級 | 精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
| 精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの | |
障害手当金 | 精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
日常生活の状況等を重視し総合的に認定
精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、具体的には以下の状態に基づいて等級が判断されます。
日常生活が、おおむねベッドで就床している程度のものは、1級です。
日常生活が、著しい制限を受けるか又は、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものは、2級です。
労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものは、3級です。
労働が制限を受けるか又は、労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものは障害手当金に該当します。
■ 認定要領
精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様であリます。
したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、 その原因及び経過も十分判断材料とされます。
精神の障害は
①「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」
②「気分(感情)障害」(そううつ病とも言う)
③「症状性を含む器質性精神障害」
④「てんかん」
⑤「知的障害」
⑥「発達障害」に区分する。
症状性を含む器質性精神障害、てんかんであって、妄想、幻覚等のあるものについては、 「A 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害」に準じて取り扱う。
(1)・「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」(F20-29)
並びに
・「気分感情障害」(そううつ病)(F30-39)
 障害の程度
障害の程度
各等級に相当すると認められる障害の状態
| 障害の程度 | 障害の状態 |
| 1 級 | 1. 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状が 障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、 ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの |
| 2 級 | 1. 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格 2.気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及 |
| 3 級 | 1. 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変 化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が あり、労働が制限を受けるもの 2.気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及 び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続した り又は繰り返し、労働が制限を受けるもの |
 発病からの症状の経過観察
発病からの症状の経過観察
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害の認定に当たっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。
ア. 統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害
の状態に該当すると認められるものが多い。
しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。
したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。
イ. 気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すも
のである。
したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。
また、統合失調症等とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、 併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
 社会生活
社会生活
日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を充分確認したうえで、日常生活能力を判断すること。
 人格障害は除外
人格障害は除外
人格障害は、原則として認定の対象とならない。
 神経症でも精神疾患は対象
神経症でも精神疾患は対象
神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則と して、認定の対象とならない。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。
(2)症状性を含む器質性精神障害(F00-09)
 中枢神経障害による症状性
中枢神経障害による症状性
症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害を含む。)とは、先天異常、頭部外傷、変性疾患、新生物、中枢神経等の器質障害を原因として生じる精神障害に、膠原病や内分泌疾患を含む全身疾患による中枢神経障害等を原因として生じる症状性の精神障害を含むものである。
なお、アルコール、薬物等の精神作用物質の使用による精神及び行動の障害(以下「精神作用物質使用による精神障害」という。)についてもこの項に含める。
また、症状性を含む器質性精神障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
 障害状態
障害状態
各等級等に相当すると認められる障害の状態。
| 障害の程度 | 障 害 の 状 態 |
| 1級 | 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの |
| 2級 | 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
|
3 級 | 1. 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの 2. 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの |
| 障害手当金 | 認知障害のため、労働が制限を受けるもの |
 脳障害は精神と神経を総合判断
脳障害は精神と神経を総合判断
脳の器質障害については、精神障害と神経障害を区分して考えることは、その多にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合して、全体像から総合的に判断して認定する。
 薬物等急性中毒は対象外
薬物等急性中毒は対象外
精神作用物質使用による精神障害
ア. アルコール、薬物等の精神作用物質の使用に より生じる精神障害について認定する もので精神病性障害を示さない急性中毒及び明らかな身体依存の見られないものは、認定の対象とならない。
イ. 精神作用物質使用による精神障害は、その原因に留意し、発病時からの療養及び症 状の経過を十分考慮する。
 高次脳機能障害は経過観察
高次脳機能障害は経過観察
高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となる。
その障害の主な症状としては、失語、失行、失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがある。
なお、障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転も見られることから療養及び症状の経過を十分考慮する。
また、失語の障害については、「 言語機能の障害」の認定要領により認定する。
 社会的な適応レベル
社会的な適応レベル
日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を充分確認したうえで、日常生活能力を判断すること。
(3)てんかん(G40)
 重症度・発作頻度の他、精神神経症や認知障害にも留意
重症度・発作頻度の他、精神神経症や認知障害にも留意
てんかん発作は、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などに分類されるが、 具体的に出現する臨床症状は多彩である。
また、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまで様々である。
さらに、てんかん発作はその重症度や発作頻度以外に、発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、稀ならず出現することに留意する必要がある。
 等級ごとの障害状態
等級ごとの障害状態
各等級に相当すると認められる障害の状態。
| 障害の程度 | 障害の状態 |
| 1級 | 充分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上ありかつ、常時の援助が必要なもの |
|
2 級 | 充分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの |
| 3級 | 充分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの |
(注1)発作のタイプは以下の通り
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
(注2)てんかんは、発作と精神神経症状及び認知障害が相まって出現することに留意
が必要。
また、精神神経症状及び認知障害については、前記「B症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定すること。
 日常生活と社会生活
日常生活と社会生活
てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性 や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれるがである。
そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定する。
様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には、治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
また、てんかんとその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
 投薬・外科的治療は対象外 てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象にならない。
投薬・外科的治療は対象外 てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象にならない。
(4)知的障害(F70-79)
 特別援助
特別援助
知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう。
 障害状態
障害状態
各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
| 障害の程度 | 障害の状態 |
1 級 | 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの |
| 2級 | 知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの |
| 3級 | 知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの |
 援助の必要度
援助の必要度
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。
また、知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
 社会生活の適応性
社会生活の適応性
日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
 一部就労も可
一部就労も可
就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。
したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
(5) 発達障害(F80-98)
 低年齢から発症
低年齢から発症
発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、 注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。
 コミュニケーション能力
コミュニケーション能力
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができない。
そのために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。
また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加 重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
 20歳以降の初診日
20歳以降の初診日
発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。
 障害等級
障害等級
各等級に相当すると認められる障害の状態。
| 障害の程度 | 障害の状態 |
| 1級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの |
| 2級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの |
| 3級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの |
アスぺルガー症候群って?
能や言語に問題はないものの、職場やプライベートで「常識がない」、「相手の気持ちを理解できない」などと非難されてしまう場合があります。
 脳の発達障害
脳の発達障害
それらの症状は、もしかしたらアスペルガー症候群かもしれません。アスペルガー症候群は心の病気ではありません。脳の発達障害によるものです。
 うつ病等の2次障害の危険
うつ病等の2次障害の危険
アスペルガー症候群の症状は、子どもの頃は個性として捉えられても、大人になってから社会生活を送る上でトラブルの原因となり、適切なケアを受けずにいると、ストレスからうつ病や強迫性障害などの二次障害を引き起こす危険があります。
 子どもの頃からの個性はアスペルガーの症状
子どもの頃からの個性はアスペルガーの症状
アスペルガー症候群は、子どものうちに適切な診断を受けることが望ましいですが、大人になるまで発見されないことが多いのが現状です。
「職場の電話に出ても、会話をしながらメモがとれない」「人の目が気になって仕事に集中できない」など、一見、本人の努力次第のように見える行動も、アスペルガー症候群の症状です。
アスペルガー症候群の主な症状
- コミュニケーションが苦手
- 同時に二つの作業ができない
- 自分のルールに強くこだわる
- 予定外のことに対応できない
- 興味関心の対象が限定的
- 音に過剰反応する
アスペルガー症候群と診断されたら?
「発達障害外来」や「アスペルガー症候群外来」などの専門医に受診すること
これらの外来の設置数は少ないので、総合病院などの「精神科」を受診します。電話などでアスペルガー症候群の専門医がいるかどうかなど事前に確認しておくと良いでしょう。
避けなければならない二次障害
アスペルガー症候群であることを理解されないままストレスを抱えていると、さまざまな精神疾患を引き起こす可能性があります。
二次障害は、うつ病、強迫性障害のほかPTSD睡眠障害、摂食障害などです。
アスペルガー症候群の症状を根本的に治療する薬や手術はありませんが、二次障害などの症状を軽減するためには、抗うつ剤や気分安定剤などが用いられます。
正しい理解と適切なサポート
二次障害を避けるためには、家族はもちろん、医師やカウンセラーなどの理解者を見つけることが大切です。
また、規則正しい生活を送り、休息をとることも必要になります。生活のリズムが崩れると、精神的にますます混乱を招いてしまうためです。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所では、障害年金の手続きを初め、「発達障害者支援センター」とも連携し職業訓練や、障害に理解のある職場の紹介などのサービスも視野にサポートさせて頂きます。
あきらめないで、障害年金受給しましょう!

障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。
一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
無料相談・お問合せはこちら
横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
障害年金の講習会
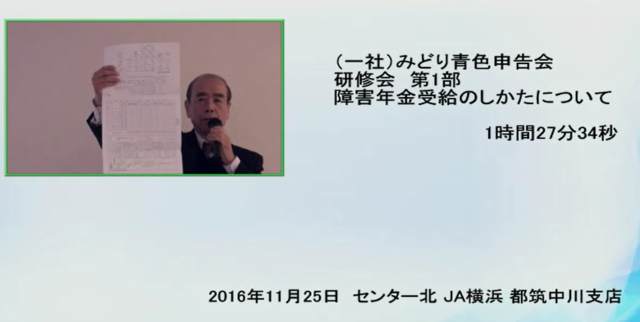
JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
ごあいさつ
資格
- 2010年 社会保険労務士資格取得
- 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
- 2014年 特定社会保険労務士付記
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
 等級判定のガイドラインの検討について
等級判定のガイドラインの検討について