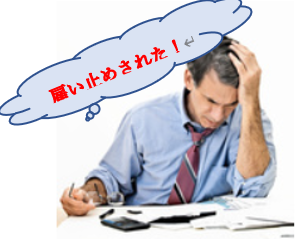運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所
〒224-0007 神奈川県横浜市都筑区荏田南1-19-6-655
脳血管疾患、脳梗塞等の認定日と申請事例出し
障害年金受給者で、腎疾患の次に多いのが脳血管疾患です!


患者数は、全国で123万人!
※H23年患者調査の概況・厚生労働省
脳梗塞、脳内出血、など脳機能に不可逆的なダメージをのこします。
救命された場合、急性期(約3ケ月)を過ぎますとリハビリテーション病院(数カ月~長くても1年ほど)へ転院させられ、専門的なリハビリテーションを行い自宅へ戻ります。
この時点でほぼ固定となります。
症状の固定時期(障害認定日)について、平成24年9月に改正されましたので、以下をご覧ください。
尚、身体に麻痺が残る場合、退院時に多くの方が身体障害者手帳を取得します。
脳梗塞等の脳血管疾患の障害認定日の取り扱い
脳血管疾患の認定基準が、平成24年9月に改正!
障害認定日は「脳血管障害により、機能障害を残しているときは、初診日から6か月を経過した日以後に医学的観点から、それ以上の機能回復が殆ど望めないと認めるとき」と改正されました。
脳血管疾患の場合、医学的に6ケ月以内は症状の固定がないとされていますが、6ケ月が経過すれば必ず症状が固定されるとみなされるわけではありません。
例えば、身体機能障害が残り、これ以上リハビリテーション等を行っても機能回復が望めないことを医学的に確認されなければなりません。
尚、リハビリテーションの目的が、機能回復か現状維持の為なのかを慎重に判断しなければなりません。
治った日の記載を確認
診断書の表面の「傷病が治ったかどうか」の欄で「治った日」に日付が記載され、「確認」とされている事。
症状固定を確認
診断書の裏面の「予後」の欄は、症状固定が確認できるような記事があること。
機能回復訓練の終了を確認
診断書に機能回復のリハビリが終了している旨の記載があること。
脳障害での障害年金申請の事例
申請事例をご紹介いたします。
当事務所からのコメント
初診日の特定は、救急車で搬送された日の為特に問題ありませんでした。
但し相談を受けた時期は、初診日から1年6ケ月経過してから約2ケ月を経っておりましたので、障害認定日請求の為直ぐに病院にて診断書の依頼しました。
約1ケ月後診断書が出来ましたが、記入漏れや性別が間違っていたり、又車いすが利用できない理由が医師に通じていなくて診断書の訂正を2度ほどお願い致しました。
申立書を作成期間中に冠動脈が10分の1に閉塞してきており医師からは、時間の問題と言われました。
手術するにも脳内出血の治療(血液の凝固薬が要)と心臓カテーテル(血栓溶解剤が要)との手術は、全く正反対の投薬を必要とする為、当該病院では不可能と告げられました。
治療方法としては高度な血管バイパス手術しかなく、高額の医療費もかかるとの事でした。
障害年金の申請が成功すれば、手術代が高額でも治療が受けられる為、請求後の認定決定が通知されるまで、神に祈る思いで待っていました。
予定よりも早く1級認定の連絡がありホットしました。
その後バイパス手術も無事成功し、今は元気にリハビリ訓練をしているとのことです。
今回の申請でのポイントは、つぎのとおりです。
救急搬送のため初診日の特定が容易に出来た
約10年前にくも膜下出血の既往歴がありましたが、特に因果関係がなく今回の緊急入院が初診日となりました。
認定日請求が出来たこと
相談に来られた時期はたまたま、初診日から1年半経過してから間がなかった為、認定日請求までに間に合ったこと。
本人様は、認定日請求の意味が分かっていなく、これからは何事も早く社労士さんに相談にきますとのコメントを頂きました。
全く就労が出来ない状態
左片上下肢が全く麻痺状態で、心臓狭窄症も併発しており今後も心臓の手術をしなければ危険な状態。
日常生活において、家族の援助が必要
洗顔、入浴、排便、歩行等日常生活において家族の援助が必要でした。
今回の申請でのポイントは、つぎのとおりです。
救急搬送された日が初診日となった
会社員である為、厚生年金での請求。保険料納付要件もOK。過去通院歴もなく診断書での初診日証明となります。
手足が不自由なため、労働は出来ないこと
身体が不自由となり、車椅子生活を余儀なくされた。常時筋肉がこわばるためリハビリ訓練が必要でした。
日常生活において制限があり、家族の援助が必要
身体が不自由なため、平衡機能がなく、歩行ができない状態です。車椅子での外出には家族の援助が必要です。
日常生活において、着替え、洗顔、トイレ、等家族の援助が必要です。
以上のポイントが認定材料とされました。
今回の申請でのポイントは、つぎのとおりです。
救急搬送された日が初診日となった
通勤途中に発病し緊急入院のため、その日が初診日となったことです。
認定日請求が出来たこと
緊急入院した病院と同じ病院で通院いていたため、1年6ケ月目の診断書が入手できたことです。
左片麻痺、言語障害のため、労働は不可となった
左片が完全に麻痺、言語障害も残り就労は全く出来なくなりました。
日常生活において、家族の援助が必要
他人との対話が満足に出来ない。また着替え、食事、洗顔等家族の援助が必要です。
脳内出血による障害年金裁決判例
これは、高血圧と脳出血との因果関係が認められ、裁判で容認された事例です。
「A氏は、脳内出血により障害の状態にあるとして、障害年金の請求をしました。
診断を受けたのは、平成5年6月のことであり、同年の3月には退職していました。
よって被保険者期間内の初診日ではないことから、支給の認定はされませんでした。
A氏は、かねてから高血圧(190/100mmHg)を医師より指摘されており、平成4年12月にめまい、頭痛で欠勤していました。
血圧の異常な上昇が認められ降圧剤も全く反応せず、自律神経的に不安定が続いたことから、退職したのです。
医師は、この発作につきCT画像上明らかな脳出血の所見は認められなかったとしていました。
しかし発作の状況、又この6か月後に脳内出血を発症していることから、一過性虚血発作であり、脳内出血との因果関係が相当濃いと判断されました。
よって、障害厚生年金の受給が決定されたケースです。
相当因果関係の総合的な判断
一般的には、高血圧と脳出血、脳梗塞は相当因果関係がないとされています。
しかし一過性脳虚血発作、可逆性虚血性神経障害及び高血圧性脳症の先行等の場合は、総合的な判断がとられます。
高血圧の指摘が医師よりあったこと
初診日より以前に、医師から高血圧の指摘を受けていたことです。病院の履歴は、忘れずにしっかりと残しておくことが必須です。
A氏の場合、関連性が認められ厚生年金加入中に医師より指摘された日が初診日となりました。
脳障害による肢体の機能障害認定基準
■ 肢体の機能の障害については、次のとおりです。
1 認定基準
| 障害の程度 | 障 害 の 状 態 |
|
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常ほとんどがベッドでの生活と同程度以上と認められる状態であって日常生活が、おおむね寝たきりの程度のもの |
|
2級 | 身体の機能の障害が、必ずしも家族の助けを借りる必要はないが、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの |
3級 | 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
■ 認定要領(日本年金機構)
第4肢体機能障害として認定
肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷等の脊 髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の場合には、「第1 上肢の障害」、「第2 下肢の障害」及び「第3 体幹・脊柱の機能の障害」に示したそれぞれの認定基準と認定要領によらず、「第4 肢体の機能の障害」として認定する。
身体機能を総合的に認定
肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日 常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。
なお、他動可動域による 評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛 緩性の麻痺となっているもの)については、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。
等級別障害状態の例示
各等級に相当すると 認められるものを一部例示すると次のとおりである。
| 障害の程度 | 障 害 の 状 態 |
| 1級 | 1. 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの 2. 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの |
2級 | 1. 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの 2. 四肢に機能障害を残すもの |
| 3級 | 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの |
(注) 肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の範囲内に限 られている場合には、それぞれの認定基準と認定要領によって認定すること。
なお、肢体の機能の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合であって、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定すること。
日常生活の動作と身体機能との関連
日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することができないが、 おおむね次のとおりである。
ア. 手指の機能
(ア) つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
(イ) 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
(ウ) タオルを絞る(水をきれる程度)
(エ) ひもを結ぶ
イ .上肢の機能
(ア) さじで食事をする
(イ) 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ) 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ) 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
(オ) 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ) 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
ウ. 下肢の機能
(ア) 片足で立つ
(イ) 歩く(屋内)
(ウ) 歩く(屋外)
(エ) 立ち上がる
(オ) 階段を上る
(カ) 階段を下りる
なお、手指の機能と上肢の機能とは、切り離して評価することなく、手指の機能は、上肢の機能の一部として取り扱う。
身体機能障害のレベルと日常生活障害との関係
身体機能の障害の程度と日常生活における動作の障害との関係を参考として示すと、次のとおりである。
ア. 「用を全く廃したもの」とは、日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいう。
イ. 「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいう。
ウ. 「機能障害を残すもの」とは、日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいう。
あきらめないで、障害年金受給しましょう!

障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非無料相談をご利用ください。
無料相談・お問合せはこちら
横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
障害年金の講習会
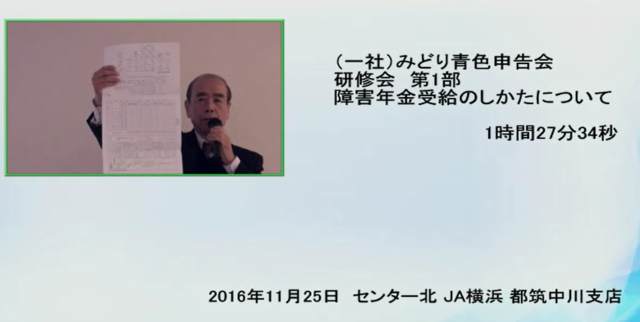
JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
ごあいさつ
資格
- 2010年 社会保険労務士資格取得
- 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
- 2014年 特定社会保険労務士付記
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。