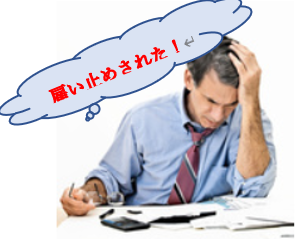運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所
〒224-0007 神奈川県横浜市都筑区荏田南1-19-6-655
障害年金Q&A
よくあるご相談
夫は7年前の会社の健康診断で腎臓病と診断され、人工透析治療を受けていましたが、先日49歳でなくなりました。
3年前会社退職後は、経済的にも苦しく、国民年金は未納になっていました。そのため年金事務所から「保険料納付要件(原則・特例)を満たしていないため、遺族年金を請求しても受けられません」と言われました。
18歳未満の子供が1人おります。何とか遺族年金を受けられる方法はないでしょうか?
障害年金の受給資格があります。
死亡した時、国民年金保険料が未納で保険料納付要件は満たしていません。又初診日から7年後の死亡のため、遺族年金は受けられません。
しかし、人工透析を受けていたとの事で、ご主人は障害年金の受給資格があったと思われます。
人工透析は1級又は2級に該当しており、その死亡の原因となった傷病と初診での傷病の因果関係が認められれば、妻に遺族基礎年金・遺族厚生年金と夫の障害厚生年金の未支給分も請求できます。
障害年金の受給後、有期認定の人は1~5年に1回更新手続きがあります。
更新の結果、障害年金が支給されなくなり、その後障害の程度が、再び重くなれば再請求しないといけないのでしょうか?
再請求は必要ないです。
いいえ、再請求は必要ありません。
更新で障害年金が支給されなくなった「支給停止」ということは、障害の程度に該当しなくなったからです。
最初に裁定請求をした時点で、障害年金の受給権が、日本年金機構から認められたのですから、同じ傷病で再請求の必要がありません。
一度支給決定を受けた受給権は、そう簡単にはなくなりません。
では、再び障害が重くなったらどうするのでしょうか?
その場合は、「支給停止事由消滅届」を診断書と一緒に提出します。
あくまでも、障害年金の支給停止と受給権が消滅することとは同じではありません。
障害年金が振り込まれなくなったから、もう二度と障害年金をもらえないなどと、勘違いしないようにしましょう。
しかし、つぎの2点にはくれぐれもご注意してください。
- 65歳に達した時に3級以上に該当しなくなって既に3年が経過していた時
- 65歳に達した以後3級以上に該当しなくなってから3年が経過した時
上記の場合は、受給権が消滅(失権)します。
従って、この受給権が消滅した後に障害の程度が再び重くなっても支給されることはありません。
次に支給の差し止めとは「障害状態確認届」のような提出期限のある書類が送られてきますが、その書類を期限までに提出しなかった場合に一時差し止めをされることを言います。
この場合は、書類を提出し障害の状態であると確認されると再度支給されます。
支給停止に納得できない方は、当サイトの不服申立ての流れをご覧ください。
有期認定の障害年金の受給者は、1~5年の間に更新手続きが必要です。
更新の際には、医師に診断書(障害状態確認届又は障害状態及び生計維持確認届)を作成してもらい日本年金機構に提出します。
裁定請求時には支給決定まで、障害基礎年金は約3か月、障害厚生年金は約5か月かかります。
では、更新時はどのくらいかかるのでしょうか?
3か月ほどお待ち下さい。
およそ、3か月くらいかかるようです。
なぜ、そんなにかかるかというと、裁定請求の時と同じように診断書の内容を審査しているからです。
でも、3か月もかかったら、その間障害年金は振り込まれないのだろうかと心配になりますね。
障害年金は、とりあえず引き続き2か月に1回偶数月に振り込まれます。
ですので、その点はご安心してください。
障害基礎年金を受給している人に、生計維持している18歳未満の子供(高校生で卒業する3月末までの人)がいる場合、障害基礎年金に子の加算が加算されます。もしも、障害基礎年金を受給されている方が離婚をした場合、子の加算はどうなるのでしょうか?
子どもを生計維持していますね。
子どもを生計維持していれば、子の加算は継続されます。
児童扶養手当と両方は?
また、離婚して18歳未満の子供(高校性で卒業する3月末までの人)を養育しているひとり親家庭には、児童扶養手当が支給されます。
果たして、両方とももらえるのでしょうか?
両方はもらえません。
残念ながら、両方はもらえません。
従来はひとり親家庭の場合は、子の加算が優先され、児童扶養手当は支給されませんでした。
H23年4月以降は、どちらか高い方を選択できるようになりました。
(※ H23.1.26 年管管発0126第2号)
H26年4月より改正があり、変更になっています。
今回の改正により、公的年金等(子の加算)が優先的に受給され、その額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分の手当が受給できるようになりました。
その点だけは、注意しましょう。
障害年金は、必ずしも就労を禁止していません。
ですから、障害年金を受給しながら働いていらっしゃる方も大勢います。
では、そのような方々の社会保険料はどう決められるのでしょうか?
社会保険料には影響ございません。
健康保険・厚生年金保険に加入している方の社会保険料は、毎年7月に4月~6月までの給与の平均額を計算し、標準報酬月額を決めます。
その標準報酬月額に基づいて、社会保険料を支払うことになります。
毎年ですから、年に1回は給与の増減によって見直しされることになります。
つまり、社会保険料は給与と賞与(賞与は賞与額で計算します)により保険料額が決まります。
もしかして、障害年金をもらっている方が、障害年金分が社会保険料に影響するのではないかと心配されるかもしれません。
障害年金は、社会保険料には一切影響を及ぼしません。
安心してもらっていて大丈夫です。
年金には時効があります。年金をもらう場合の時効は5年です。
つまり、認定日請求で10年前に遡って受給権が認められたとしても、年金をもらえるのは5年分だけです。
では、障害年金を請求するには時効があるのでしょうか?
時効はありません。
障害年金の請求には、時効はありません。
障害認定日から5年や十年以上経っていたとしても請求はできます。
障害年金は認定日請求であれば、65歳前に初診日があれば請求できますし、事後重症請求は65歳前であれば請求できます。
しかし、初診日から何年、何十年も経っていると、初診日の証明や障害認定日の診断書を取得することは、困難になります。
5年を遡っての認定日請求が認められたとしても、もらえる年金は5年間だけです。
認定日請求と同時に事後重症請求も請求し、事後重症請求しか認められなかった場合、裁定請求月以前の分はもらえません。
ですので、障害年金の請求に時効はないといっても、早めに請求された方がいいと思います。
初診日の証明が取れないと請求できませんので、根気強くやりましょう。
障害年金を請求するには、初診日を特定しなければなりません。
特定できないと障害年金の請求書類を受け取ってもらえません。
では、どのようにすれば初診日の証明は取れるのでしょうか?
大事な証明ですので、ご相談下さい。
最初からずっと同じ病院にかかっている場合は、障害年金請求用の診断書で、現在通院している病院に初診日を証明してもらいます。
しかし、初診日から10年以上も経って、色々な病院を転医している場合など、初診日の証明を取るのが困難な場合もあります。
そのような場合は、初診日の病院で受診状況等証明書がとれなかったら、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出します。
そして、次に受診した病院で受診状況等証明書を書いてもらいます。
次の病院がだめだったら、またその次の病院で書いてもらうというように、ひとつひとつあたっていくしか方法はありません。
初診日の証明が取れないと請求できませんので、根気強くやりましょう。
是非専門家にご相談下さい。
2級以上の障害年金を受給している方に、18歳(18歳の誕生日から最初の3月31日まで)の子供がいる場合、加給年金額が加算されます。
もし、子どもの加算が付くことを知らずに加算手続きをしていなかったとしたら、遡及して加給年金額がもらえるのでしょうか?
もちろんです。
もちろん、もらえます。また以下の場合も同じです。
- 2級以上の障害年金を受給していた人に、平成23年4月以降に子どもが生まれて何も手続きをしていなかった場合。(※H23年4月 年金強化法成立)
- 障害年金の受給権を取得した当時(平成23年3月以前)は、子どもが生まれていなかったが
後に子どもが生まれたにもかかわらず、加給年金額が加算されなかった場合。
それらの場合も、平成23年4月以降加給年金を請求することができます。
裁定請求時に、該当していないと手続きを忘れてしまいがちです。
年額234,800円(3人目からは78,300円)ですが、受給できれば助かりますよね。
もし、手続きをしていないという方がいらっしゃいましたら、しっかり手続きしましょう。
そうでないと損をしてしまいますね。
障害年金の認定は、有期認定と永久認定があります。
有期認定は1年~5年の期間だけ認定され、更新の手続きが必要です。
永久認定は更新手続きは一切必要ありません。
永久認定される人ってどんな人でしょうか?
日本年金機構で審査です。
障害状態で辛い時は、永久認定になればどんなにいいかと思ってしまいますよね。
手足の切断や知的障害、手足の完全麻痺、完全に失明した人など、障害状態が変化しないと考えられる人が、永久認定になるようです。
日本年金機構で審査しますので、永久認定の基準は、社労士といえども分かりません。
しかしほとんどの方が、有期認定の対象になると思われます。
ですので、認定されてホットする気持ちはわかりますが、次の更新のために日々の生活状態を記録しておきましょう。
当事務所では記録の方法もアドバイスしています。
病気といっても様々な病気があります。
国民の三大疾病って何だと思いますか?
一般的に、癌、脳卒中・脳梗塞などの脳血管疾患、心筋梗塞などの心臓疾患と考えられる方も多いと思います。
癌、脳血管疾患、心臓疾患は死亡の原因での三大疾患です。
それでは、厚生労働省が示している三大疾患とは何でしょうか?
Ⅰ位は、精神です。
それは、1位 精神疾患、2位 心臓疾患、3位 癌だそうです。
意外ですよね。
でも、これが最近の三大疾患の共通認識だそうです。
なぜかというと、死には至らないまでも「長く働けなくなる」「生活障害が生じる」からで、これを無視していると社会保障制度が立ち行かなくなるからだそうです。
特に精神疾患は日本人の20%が一生に一度は、罹患する病気だそうです。
それだけ身近な病気です。
精神疾患で苦しんでらっしゃる方、決してあなたひとりではありませんよ。
年金制度では、ある特定の時点の障害の状況を「現症」といいます。
つまり、障害認定日の診断書では、障害認定日から3か月以内の受診した日の状況を書いてもらうことになります。
また、裁定請求日の診断書は、裁定請求日以前3か月以内の受診した日の状況を書いてもらうことになります。
なぜ、3か月という期間が出てくるかというと、必ずしも障害認定日に受診するとは限りません。受診時に診断書を依頼しても、診断書をもらうまでに2~3週間かかったりしますから、それなりに日数に幅を持たせないと大変です。
ですので、現症の年月日と診断書作成日は違います。
障害年金は、障害状態が障害等級に該当している方に支給します。
1級は、日常生活に著しい支障があり、かつ他人の介助を必要とします。
2級は、日常生活に支障がありますが、最低限の生活レベルであれば、辛うじて1人暮らしができる程度です。
3級は、労働について、例えば労働時間や職務内容等に制限がある場合です。
障害年金をもらいながら働いている方は、結構いらっしゃいます。
しかし、2級の精神障害の場合、就労したら不正受給になるのでしょうか?
医師に正確な情報を伝えてください。
精神障害であっても、医師に日常生活について嘘偽りない状態を伝えて、診断書にしっかりと記載してもらえれば、たとえ就労していたとしても、不正受給とはなりません。
不正とは、実際の状態を偽って(本来よりも明らかに重い症状を申告するなど)請求することです。
精神障害の方も、福祉作業所で就労したり、パートやアルバイトで働く方もいらっしゃいます。
働いたからと言って不正受給にはなりません。
障害年金を受給中の方が、少し体調がよくなりアルバイトなりパートなりなさることがありますよね。
アルバイト先やパート先等から雇用保険に入れるよと言われた場合、雇用保険には入れるのでしょうか?
国は、障害者雇用を進めています。
雇用保険は週20時間以上働いていて、1年以上雇用されることが見込まれれば、被保険者になることができます。(行政手引20368)
そこには、障害年金を受給していたらダメ、なんて文言はありません。
そもそも、国は障害者雇用を進めたいと考えています。
障害者雇用促進法の法改正をして、障害者雇用率を1.8%→2.0%にアップしたことからも、それがわかります。
雇用保険に加入できるのであれば、加入した方がいいですね。
確定申告と言えば、障害年金は確定申告しなくてもいいの? って思われるかもしれませんね。
障害年金は、確定申告をする必要はありません。
障害年金、障害手当金等は非課税です。ついでに、遺族年金も非課税です。1円も税金がかかりません。
税金がかからないものは確定申告をする必要がないのです。
年金の中で確定申告が必要なものは、老齢年金ですが、年金額が400万以上の方たちです。
しかし、老齢年金を年400万円以上もらう方たちって、どんな方たちなんでしょうか。
とても、私の老齢年金などその半分にも及びません。うらやましい限りですね。
税金というと、訳が分からないし、面倒と感じる方が多いでしょうが、障害年金を受給されている方は、関係ありませんので、ご安心ください。
60歳~65歳未満の障害等級3級以上の人が請求すると、請求した時点から特別支給の老齢厚生年金に特例として、定額部分が加算されていました。
今度の法改正ではどのように変わったのでしょうか?
障害者の特例は、申請する必要があります。
60歳~65歳未満までに老齢厚生年金をもらえる方で、障害等級3級以上の人が、勤務していない場合、以前から特別支給の老齢厚生年金に定額部分を加算して一緒にもらえています。
但し、この障害者の特例は、申請をしないともらえません。
今までは申請をすると申請をした翌月から定額部分をもらうことになります。
今回、法律改正により申請が遅れても、特別支給の老齢厚生年金が支給開始された時点まで遡ってもらえることになりました。
例えば、60歳に裁定請求して、老齢厚生年金が支給された障害者3級以上の人が、まるっきり制度を知らずに63歳で申請した場合、改正前は63歳からしか定額部分がもらえませんでした。
改正後は60歳まで遡って定額部分がもらえることになります。
今までは、知らないで損をしている方もいたかもしれませんが、これで損をすることはなくなりますね。
障害年金については、早めに専門家に相談しましょう。
障害手当金は最低保障額の2年分ですが、障害の軽い人がどうして2年分と多くもらえるのでしょうか?
下記を参考にしてください。
障害厚生年金には、1級、2級、3級と障害手当金があります。
現在、3級の最低保障額は612,000円です。(R6年度)
障害手当金の最低保障額は612,000X2=1,224,000円です。
ちょっと見ると、3級よりも障害手当金の最低保障額の方が多いと感じますよね。しかし、そうとは限らないのです。
3級は金額が少なくても、年金なので更新するまではもらえますし、障害が憎悪した場合さらに上位等級に改定されます。
障害手当金は、傷病が治癒又は固定しているので、年金ではなく一時金(1回のみ)でもらうことになります。
一時金として障害厚生年金の2年分を1回もらうより、年金でもらった方が長い目で見れば年金額は多くなります。
その為、障害手当金の最低保障額が多く設定されています。
精神疾患の場合、検査数値等の客観的な診断基準がないため、診断書の内容が医師の主観に左右され、実態の障害の程度と違った診断書をかかれる場合もありますので、以下の3ポイントをチェックしましょう。
【傷病名についてチェック】
なぜなら、精神疾患の場合原則として神経症と人格障害については、障害年金の対象としないとされているからです。(F4~F6)
傷病名の欄が神経症や人格障害だけの場合、障害年金の受給は難しくなります。
うつ病や統合失調症などの症状も出ている場合は、傷病名の欄に追加してもらったり、備考欄に記載してもらったりすることができれば、障害年金の対象となります。
【日常生活状況についてチェック】
日常生活を送るあらゆる場面で、他人の援助(介助)が一部又は全部必要な度合が判断材料です。
【現症時(請求時点から3月以前まで)の日常生活活動能力及び労働能力をチェック】
医師が、日常生活能力と労働能力についてコメントする欄です。
例えば2級を狙う場合に「軽労働は可能」などと記載されると、労働能力ありと見なされる場合があります。
他にも日付や、申立書との整合性などチェックすべき点はありますが・・・・
障害年金の受給の可否に大きな影響があるのは、以上の3ポイントでしょう。
もらえる障害年金の種類は、初診日に加入していた年金制度により決まります。
例えば、子どものころに初診日があって、その後成人してから厚生年金に加入したとしても、もらえる年金は障害基礎年金ですね。
また、反対に会社に勤めている間に初診日があり、その後退職したとしても、請求できる年金は障害厚生年金ですよね。
子どもの頃に初診日があったとしても、厚生年金に加入したんだから障害厚生年金をもらいたいと思うかもしれませんが。
この場合は社会的治癒(当サイトの社会的治癒参照)が認められないと厳しいです。
ただ、加入している厚生年金は、将来の老齢年金のもとになりますから、損をすることはありません。
年金制度は、保険制度のひとつだということをしっかり理解して頂くといいですね。
そうすれば、障害になっても正々堂々と請求する気持ちになれますから。
民間の生命保険は、加入して保険料を払っているからこそ、契約範囲で保険給付します。
障害年金もそれと同じです。
(この辺が身体障害者手帳と混同するところかもしれません)
障害年金を請求する際、初診日を証明する受診状況等証明書と診断書は必要です。
受診状況等証明書に書かれている傷病名と診断書に書かれている傷病名が、違っていることがあるんですが。
特に精神疾患の場合などに多く見られます。
そのような場合、どうしたらいいのでしょうか?
精神の場合よくあることです。
有期認定の障害年金を受給している人は、1~5年に1回、誕生日のある月の月末までに更新の手続きしなければなりません。
「20歳前傷病」による障害基礎年金を受給している人は、誕生日のある月ではなく、毎年7月末までに更新手続きをします。
もし、更新の手続きが月末を過ぎてしまったら、どうなるのでしょうか?
診断書を入手したら、すぐ更新しましょう。
そのまま放っておいたら、障害年金の振込はストップします。
障害年金が、振り込まれないと困りますよね。
診断書の出来上がりが、月末までに間に合わない場合でも、入手次第手続きをしてください。
また、そのまま何年間にもわたって、更新の手続きをとらないでいると、手続きをするまで毎年の診断書を求められてしまいます。
障害年金と介護保険は、目的が違いますから、当然利用できます。
40歳以上で、次の疾患が原因であればOKです。
① 筋萎縮性側索硬化症
② 後縦靭帯骨化症
③ 骨折を伴う骨粗しょう症
④ 多系統萎縮症
⑤ 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
⑥ 脊髄小脳変性症
⑦ 脊柱管狭窄症
⑧ 早老症(ウェルナー症候群等)
⑨ 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
⑩ 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
⑪ 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
⑫ 閉塞性動脈硬化症
⑬ 関節リウマチ
⑭ 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
⑮ 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
また、65歳以上であれば、傷病の原因を問わず、利用できます。
介護保険の介護サービスを受けるには、お住まいの市区町村で介護認定を受けなければなりません。なぜなら、介護保険を運営しているのは市区町村だからです。
認定を受ける際は、障害年金の診断書を作ってもらうときと同じように、「日常生活でどのようなことが出来ないのか」ということをしっかり伝えてください。
そうでないと、介護度を軽く認定されてしまったりしますからね。
障害年金を請求し、認定されると障害年金がもらえます。
それは、障害年金の受給権を得たからなのです。
障害年金の受給権と支給を受ける権利は、違うものなのでしょうか?
違うものです。
実は、違うものなのです。
受給権は、裁定請求して認定されれば死ぬまでなくなりません。
ただし、65歳になった時に3級に該当しないまま3年経過したときは、受給権はなくなります。
一方、支給を受ける権利は、更新時に障害状態に該当しないと判断されれば、なくなります。
つまり、受給権があっても障害年金をもらうことができなくなるのです。
また、遡及請求で障害認定日が5年よりもずっと前である場合、受給権が障害認定日に発生しても、障害年金の支給を受けることができるのは5年間しか遡りません。
これは、受給権と支給を受ける権利が違うからなんですね。
障害年金をもらえなくなると、受給権がなくなったからと思いがちですが、全く違いますので間違えないようにしましょう。
障害年金の請求でポイントになるものに初診日があります。
初診日は、障害の原因となる傷病について、初めて医師または歯科医師の診断を受けた日です。
では、健康診断で異常が見つかった場合は、どうなるのでしょうか?
健康診断日が初診日です。
健康診断の結果、受診を指示された場合は、健康診断日が初診日になります。
但し、健康診断後に最初に受診した病院で受診状況等証明書が入手できる場合はこの限りではありません。
尚、健康診断で経過観察といわれた場合は、残念ながら初診日にはなりません。
初診日を特定するのは大変な作業ですから、是非参考にしてください。
障害厚生年金には、1級から3級まであり、その他に障害手当金があります。
現在、障害厚生年金を受給している人に、別の傷病が発生した場合、障害手当金はもらえるのでしょうか?
別の傷病であれば支給されます。
別の傷病であれば、もらえます。
例えば、うつ病で3級の障害厚生年金をもらっている人が、事故により人差し指を失った場合、初診日に厚生年金に加入しており、初診日から5年以内に傷病が治癒又は固定していれば、障害年金とは別に、障害手当金をもらうことができます。
障害手当金には、障害認定日はありません。
初診日から5年以内に傷病が治っていればOKです。
また、障害手当金は別の傷病であれば、何回でも請求できます。
別の傷病で障害年金をもらっているから、障害手当金はもらえないなんて考えないようにしましょう。
障害年金は、生活設計の基本です。仕事が出来ず収入を絶たれた申請者にとっては、非常に重要なことです。
申請から支給開始されるまで、どのくらいの時間が必要なのでしょうか?
決定通知まで3か月ほど時間がかかります。
申請に必要な書類を整え請求書を提出してから、申請者宅に通知の郵便物が届きます。
「年金証書」および「年金決定通知書」が送付されるのですが、国民年金の場合は請求書を提出してから約3ヶ月かかります。厚生年金(共済)の場合は、約4~6ヶ月です。
(H29年4月以降障害年金センターで一括審査されるため、約4~6ケ月かかるでしょう)
また実際に支給開始されるのは、「決定通知書」が届いてから1~2か月後となります。
以上を合わせますと、申請から支給開始されるまで、約4~8ヶ月かかるということになります。
勿論個人差があり、はやく認定される場合もあります。
国民年金ですが、過去に未納があります。又免除の申請も怠っています。障害があるのですが申請出来るのですか?
条件に値すれば、申請可能です。
年金加入期間(被保険者期間)のうち、納付期間と免除期間を合算した期間が、3分の2以上あるか、または初診の前々月以前1年間滞納していなければ、過去にいくら滞納していても申請は可能です。
怪我で右人さし指をなくしました。障害の程度が軽いので障害手当金を請求しようと思います。どのような条件が必要なのでしょうか?
以下の条件があります。
障害手当金(障害一時金)は、病気や怪我などで軽い障害がある場合に支払われる制度です。
つぎの4つの条件を満たせば受給できます。
- 初診日の時に厚生年金保険(共済年金保険)に加入している方が、対象です。
- 初診日から5年経過するまでに、傷病が治ったこと(症状が固定)です。
- 傷病が治った日に一定の障害状態であることです。政令で定める障害認定基準に該当しなければ、受給できません。
- 初診日の前日において、一定の保険料納付要件を満たしていることです。
- 被保険者期間のうち、納付済期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上あること
- 3分の2以上の納付要件を満たさなくても、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に滞納がないこと
以上の要件を満たしていれば請求できます。
但し時効が5年ですので、治ってから5年過ぎての請求はできませんのでご注意ください。
公表されている認定基準では、在宅酸素療法を施行中の方で、かつ軽易な労働以外に支障がある程度のものは、3級とされています。
しかし臨床症状、検査結果、及び日常生活状況等によりさらに上位等級になる場合があるとされています。
ではどのようなケースが、2級になるのでしょう。
在宅酸素療法を施行中の動脈血酸素分圧値は、正常値の事が多いです。これはベッドで安静にしての測定ですので検査上当然ですが、ベッドから離れて違う場所に移動しただけで数値が悪くなることがあります。
日常生活に著しい制限がある場合には、軽労作のSpO2低下や運動負荷肺機能検査等が医師の診断書にしっかりと示されていれば、2級に認定される場合もあります。
私は、過去に急性肝炎になり治療していましたが、治癒し元気に働いていました。
2、3年前ですが、疲れやすいので病院に行ったところ、又急性肝炎と言われました。現在は肝硬変で入院中です。
障害厚生年金を請求したいのですが、初診日はどちらにすればよいですか?
医師の判断がポイントです。
過去の傷病が治癒したのち再び同一傷病が発症した場合は、再度発症として過去の傷病とは、別傷病として取り扱われます。
治癒したと認められない場合は、傷病が継続しているものとして同一傷病となります。
又「社会的治癒」が、認められるかどうかによっても違います。
ご質問者様の場合は、医師が病気を治癒したと判断し元気に働いていたのですから、過去の急性肝炎とは別傷病とされます。
よって2、3年前に受診した病院が初診日となります。
2年前に事故で左足を失いました。2級の障害基礎年金を受給していますが、再び事故にあい今度は右足が麻痺しています。
受給している年金のほかに、新たな障害基礎年金は受けられますか?
この場合は併合認定になります。
国民年金法では、同一の者が2つ以上の年金の受給権を取得した時は、原則としてその者の選択によりいずれか1つを支給したものは、他の年金は支給停止されることになっています。
しかし上記の場合、全体として見れば両下肢を失ったこととなります。前述のように一方のみの支給では、あまりにも不合理です。
この様な場合には、前後の障害を併合した等級の障害基礎年金を支給されることになります。
この方の障害状態の認定は、左足喪失の2級と右足の麻痺障害2級と「併合認定」されます。
「両下肢の用を全く廃したもの」として1級の障害基礎年金が支給されます。
胸のしこりを感じ検査しました。検査上疑いはなく経過観察といわれました。翌年出産をしましたが、乳腺のはりが酷く別の病院で検査したところ癌が発見され即手術となりました。
後遺症が酷く障害年金申請を考えています。初診日は、経過観察といわれた病院にしたいのですが?
以下をご覧ください。
この場合、今の医師がどのように診断しているかによって状況が違います。あきらかに最初しこりを感じた部分と同じ場所のがんであれば、誤診となりますね。
誤診を初診日として認めてもらえる取扱いになると、最初の経過観察と言われた病院での受診状況等証明書が有効ですが、必ずしも初診日証明を出したからと言って認められるわけではありません。
最初は経過観察で治療はありませんし、今の主治医の診断書、又病状の経過等全てを審査して初診日が決まります。
今の主治医の意見書やら少なくても最初の経過観察時点で癌の可能性を示唆する内容の書類が必要となります。
いずれにしましても診療内容をしっかりと把握したうえで、確実な書類で申請することをお勧めいたします。
「障害認定日による請求」であれば、遺族にかぎり未支給年金を請求できます。
ただし遺族とは、「生計を同じくしていた3親等以内の親族」までの範囲です。
① 配偶者 ② 子 ③父母 ④ 孫 ⑤ 祖父母 ⑥ 兄弟姉妹 ⑦ 甥・姪 ⑧ 子の配偶者 ⑨ 伯父・伯母・叔父・叔母 ⑩ 曾孫・曾祖父母 ⑪ 以上の者の配偶者
支給を受けられる順位もこの順番です。
年金事務所(国民年金加入者は市区町村役場)に行って、所定の手続きをして下さい。
詳しくは、当事務所までご連絡下さい。
58歳男性ですが、肺がんの為就労不能になりました。昨年3級の障害厚生年金支給の決定を受けました。
ところが、受給が始まった頃より急激に悪化し人工呼吸を装着するまでになりました。
「額改定は、年金の受給権が発生した日から1年を経過しないと請求できない」と言われていますが、どんな場合も請求できないのですか?
改定により条件に該当すれば、請求できます。
額改定について、平成26年4月1日から改正がありました。
確かに1年経過しなければ、額改定請求はできないですが、一定の要件に該当すれば待つことなく額改定の請求ができるようになりました。
一定の要件とは、「眼・聴覚・言語機能の障害」「肢体の障害」「内部障害」「その他の障害」に分類される22項目です。
症状が悪化し22項目に該当(人工呼吸器を装着して数か月経過)していますので、早急に専門の社労士に依頼することをお勧めいたします。
7月生まれです。障害基礎年金受給者ですが、更新の為「障害状態確認届」を提出しました。
結果不支給となりました。年金はいつから停止になりますか?
11月分より支給停止です。
障害年金は、一度決定されても永久に支給されるものではありません。
障害の状態が診査され、これまでより障害の状態が軽くなったと判断された場合、減額又は支給停止となります。
年金機構の事務処理として、支給停止の場合は、誕生月から起算して3か月を経過した翌月から支給停止となります。
7月生まれですので、11月分より支給停止されることになります。
また今後の対策として、障害の程度がその後増悪していれば、「支給停止事由消滅届」を提出する方法があります。
障害等級の1級~2級に該当する障害厚生年金の受給権者が死亡した場合は、遺族厚生年金は受給されます。
3級の場合は、支給されないことになっていますが、障害厚生年金を受けている傷病が悪化し死亡直前には、1級~2級に該当する障害状態で死亡されたのであれば、遺族厚生年金は支給されます。
平成10年に国民年金加入中に精神科に受診しましたが、主治医と折り合いが悪く通院しませんでした。
その後会社員になって、平成18年5月上司のパワハラでうつ病になり初めてメンタルクリニックに受診しました。
障害年金を申請出来ると聞きましたが、初診日は平成10年又は、平成18年5月のどちらになるのでしょうか?
平成18年5月であれば、障害厚生年金3級から受給出来ると言われました。
以下をご覧ください。
初診日は、初めて精神科を受診した平成10年となります。
但し、社会的治癒を主張することにより平成18年5月が初診日となる可能性があります。
「この場合であっても受診状況等証明書は、平成10年のものが必要となります。」
このケースは、非常によく頂く質問です。
厚生年金の方が、有利となりますのでお気持ちは分かりますが、初診日を意図的にずらして請求することは出来ません。
又診療録破棄の為、初診日を受診状況等証明書により証明出来ない場合は、原則として請求しても認められることは御座いません。
ただし診療録がなくても、その他の間接的なエビデンス(証拠となる書類)があれば認められることも御座います。
最後まで諦めずに、過去にその病院を受診したという診察券やお薬手帳、病院窓口の受付簿、レシート、転医先に持っていった最初に受診した精神科の紹介状、等の有無を確認して下さい。
初診の病院が、海外の場合であっても初診日の証明(受診状況等証明書)は必要です。
尚、海外の病院に受診状況等証明書を依頼される場合は、和訳文の添付が必要です。
障害厚生年金2級を受給中です。この度結婚をしましたが、配偶者加算は、つきますか?
生計を維持されていれば加算されます。
厚年法50条の2では、障害等級1級または、2級の受給者は、その者により、生計を維持されている配偶者がいる場合、配偶者加給年金が加算されます。
加算要件としては、配偶者が65歳未満であり、かつ収入が850万未満であることです。
但し法律上では、配偶者が大正15年4月1日以前生まれの場合は、65歳以上に達しても加算されます。
又支給停止の規定としては、配偶者が老齢年金及び障害等級3級以上の年金を受けられる場合は、支給停止となります。
主婦です。人工関節置換術しました。左足の股関節と膝関節の2か所です。
この場合は、2級になりませんか?
お問合せメニュー
障害年金のメニュー
あきらめないで、障害年金受給しましょう!

障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非無料相談をご利用ください。
無料相談・お問合せはこちら
横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
障害年金の講習会
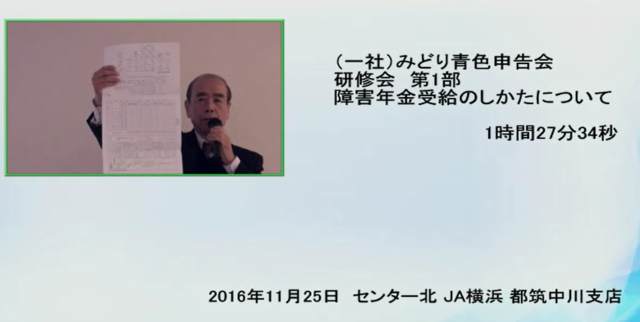
JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
ごあいさつ
資格
- 2010年 社会保険労務士資格取得
- 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
- 2014年 特定社会保険労務士付記
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。