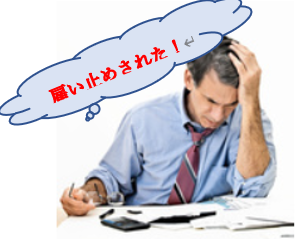運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所
〒224-0007 神奈川県横浜市都筑区荏田南1-19-6-655
当事務所の取り組み方針
この3つの方針で安心!
医師との直接面接・診断書の再チェック
障害年金は、基本的には全て文書での審査となります。障害年金の認定医が自宅や職場に来て(障害の状態なのか?や障害の程度が等級レベルなのか?)などを確認に来ることはありません。
診断書や申立書に書かれている文章や添付資料(X線フィルム)などで決められています。
ですから「障害の状態なのか?重症の程度が等級レベルになっているのか?」等をいかに医師に書いてもらうかが、非常に重要です。
「障害状態」を客観的に第三者が証明する資料は診断書ですし、障害の状態を客観的に証明できる人は、主治医に限られています。
従って、主治医の協力なしでは、障害年金の請求はあり得ません。
ところが、もしその診断書が間違っていたり、不本意な内容だったりしたら大変なことになります。
特に診断書の項目の中には診察では分からない普段の「日常生活における動作の障害の程度や活動能力」等を書く項目があります。
そのような日常生活の情報を、医師に対して正確にお伝えし間違いのないように診断書に書いてもらわねばなければなりません。
一般的に患者の立場では、主治医の手前見栄を張ってなかなか日常困っている症状を素直に話せない方も沢山いらっしゃいます。
一方、主治医にとっては、患者を治療し、病を治すことが目的ですから、障害年金請求に不慣れであるとか、障害年金用の診断書を書いたことがないとか、請求者の障害認定にどのように影響するかは一切関係のない事です。
医師との直接面談の必要性について2件の事例をご紹介させて頂きます。
1件目は、性別ミスと 、補助用具使用の件で修正をして頂いた件です。
- 性別ミスは男性の名前が「薫」でしたが、診断書には女性の項目に○がついていました。
また同じ診断書ですが、手に感覚がなく車椅子に手が挟まれる恐れがあるので、車いすの使用を禁止されていたのですが、診断書では使用可となっていました。
以上の2点を早速修正していただきました。
主治医が記入している場合は、こんな単純ミスが起こらないと思います。
医師は診察に忙しい為、書類は事務員に任せているからでしょう。
2件目は、股関節変形症で人工関節挿入後3年経過していた診断書の件です。
- 手術後3年も経過しますと、一般的に足の左右差が多少広がりますが、請求者様の場合は、約4センチでした。
つまりかなりビッコを引いて歩いており、段差のある道路ではよく躓いていたり、一般道路でもよろめいていました。
診断書の平衡機能の項目に「2. 開眼で10メートル歩行状態」を記入する欄がありそこには、次のように診断されていました。
 ア、まっすぐ歩き通す。
ア、まっすぐ歩き通す。
イ、多少転倒しそうになったり、よろめいたりするがどうにか歩き通す。
ウ、転倒あるいは著しくよろめいて、歩行を中断せざるを得ない。
早速、主治医に修正を依頼し、「イ」に無事修正して頂きました。
恐らく、患者の立場では修正の依頼は難しいのではと思います。
又いくら主治医でも、日常生活の状態までは把握できません。
このようなミスがないように、診断書を丁寧にチェックしなければなりません。
当事務所の役割として主治医と直接面談し、障害年金の認定される基準を説明したり、又請求者の日常生活の状況等を正確にお伝えします。
時には、年金機構に対して不当な認定を防止又は是正させ、障害年金の請求手続きを順調に押し進るように働きかけます。
あらゆる角度から請求者にとって最善の選択をして頂くようにアドバイスすることだと考えています。
- 1医師との面談の際の注意点を懇切丁寧にアドバイスさせて頂くこと。
- 2必要に応じてお客様とともに医師と直接面談し、日常生活の活動能力等の情報を正確にお伝えすること。
- 3診断書を鵜呑みにしないで、記入漏れや、各項目に間違いがないかを丁寧にチェックさせて頂くこと。
以上を第1の方針としております。
しっかりとした「申立書」の記入
障害年金の請求は、全て書類審査になっております。認定医や審査官は、直接請求者と面談し話を聞くことはありません。
又社会保険審査官の認定医も人間ですからあまり乱雑な文章であったり、活字が間違っていたり読みにくい文字であれば、しっかりと読んでもらえず、何度も訂正や問合せに悩ませられます。
「病歴・就労状況等申立書」は、請求者が書く書類です。
この書類は発病から治療の経過及び日常の生活状態を記入するわけですが、しっかりと丁寧に又読みやすい文章で書かなければ、社会保険審査官に真剣に読んでいただけません。
又請求の症状を、医学的な用語も駆使し障害状態を出来るだけイメージしやすいような文章で記入する必要があります。
- 1当事務所では、パソコンで読みやすいように、きれいに仕上げること。
※ 指定様式があり、殆どが手書のため誤字脱字等で読みづらい。
- 2発病に至った状況や、初診からの治療の経過と現症及び日常生活の状態等を、申立書を読む審査官の頭にイメージしやすいように医学的な表現も交えて記入すること。
以上を第2の方針としております。
受給後の徹底したアフターフォロー
障害年金は、原則として期限のある有期年金です。予め決められた時期が来ると年金機構から書類が送られてきます。それが「障害状態確認届」です。
これは、傷病の種類によって1年から5年の期間が予め決められて送られてくる書類です。
障害年金は、最初に受給したらやれやれと思われる方が多いですが、予め決められた時期がくると、当初の請求手続きと同じように書類を提出しなければなりません。
何故なら、障害の状態は途中で重くなったり、軽くなったりするからです。
精神の障害の場合は2~3年、肢体の場合それよりも多少長かったりします。
例外的に脳疾患後遺症や肢体の離断などのように医学的に障害が改善される見込みのない場合は、永久認定と言って、一生提出する必要がない場合もありますが、そのような方はごく稀です。
ほとんどの方はこの書類を提出しないと、今まで受給していた障害年金が、一時差し止められる恐れがあります。
「障害状態確認届」とは、診断書と同じく障害の状態を改めて審査を受ける手続きになります。
既に障害年金を受給しているからと言って軽視しがちですが、油断はできません。医学的に改善が困難と思われる障害でも、簡単に支給停止したり等級を下げたりしてきます。
医学的には症状が変わらないような場合や悪化して行くような場合でも、提出された医師が作成した「障害状態確認届」のほうが優先されて、決められます。
ですから、前回提出した診断書よりもすこしでも改善しているように見える場合は、支給停止又は下位等級への変更リスクが、よくあることと思わねばなりません。
例えば、知的障害や発達障害でも支給停止されたり、受給権が得られなくなることも多々あるということです。
従って、そのようなリスクを防止するためには、受給後のアフターフォローが大事になってきます。
つまり、当初の診断書を提出した時と同じように受給開始から現在までの「日常生活の状態と治療経過」を出来るだけ毎月記録しておくことです。
- 1初回受給開始後から記録の方法を懇切丁寧にアドバイスしアフターサービスを徹底すること。
- 2受給後も「その他障害」が発生したり、前後の障害を併合した手続き及び障害の程度が重くなった場合は、請求手続き等必要に応じて丁寧に手続きをさせて頂くこと。
以上を第3の方針としております。
無料相談・お問合せはこちら
横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
障害年金の講習会
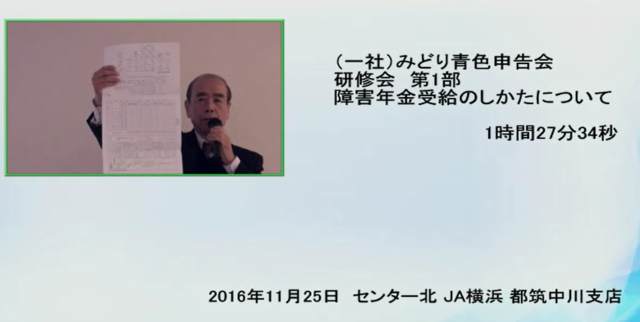
JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
ごあいさつ
資格
- 2010年 社会保険労務士資格取得
- 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
- 2014年 特定社会保険労務士付記
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。