腎疾患(人工透析の方)
人工透析療法施行中の場合は、原則2級に該当します!
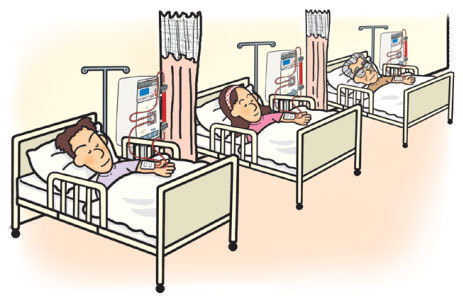
病気休職者で一番多いのが、糖尿病を患っておられる方です。
厚生労働省調査では、糖尿病の患者数が、平成26年度概況で316万人となり年々増加しています。
人工透析をされている方は、全国で、2014年末時点ですでに32万人を超えています。
この様な方は、身体障害者手帳1級をお持ちですが、障害年金を受給されていない方が、非常に多いです。
受給要件をクリアしますと、人工透析施行されている方は、「障害年金2級」も認定されます。
国の保険制度をしっかり活用しないともったいないことです。
人工透析には、血液透析・腹膜透析・血液濾過の3通りの方法があります。
どちらも認定の基準は、同様で原則2級に該当するとされております。
「透析施行中であるのに、障害年金を受け取っていない方へ」・・・・

「条件がありますが、障害年金を受給できる可能性があります。」
当事務所は、透析患者様のサポートを数多くさせていただいております。
無料診断をさせていただきますので、お気軽にまずはお電話をください。
お待ちいたしております。
「人工透析」で障害年金を受給するポイント!
糖尿病は・・・・
「発病しても急激に悪化しない」
「初期の症状から慢性腎不全及び人工透析に至るまでの期間が、非常に長く請求時点ではカルテの破棄等の理由で初診日が特定できない」
という特徴があります。
よって「初診日が分からない」「病院のカルテがない」・・・・
このような壁を乗り越えられず、あきらめる方が多いのも事実です。
当事務所には、「初診日等が分からなくても障害年金受給につながった方が、数多くいらっしゃいます。」
わずかなヒントもキャッチできるよう、じっくり時間をかけてヒアリングさせていただいています。
また、腎疾患では、初診日に関するアンケートの提出が必要です。
初診日認定の参考になる書類ですので、正確に記入する必要があります。
「人工透析を施行され、障害年金請求をお考えの方!」
腎疾患での障害年金申請の事例
当事務所の申請事例を1部ご紹介します。
- 腎硬化症による人工透析
- 糖尿病による人工透析
- 高血圧症による人工透析
- IgA腎症による腹膜透析
- 慢性腎不全よる人工透析
今回の申請での認定のポイントはつぎのとおりです。
初診日証明が出来た事
一般的に糖尿病の発病及び初診日から人工透析の開始に至るまで、約10~20年と長期に亘ります。
その為過去10年~20年前のカルテが廃棄されたり廃院している場合が多く初診日の証明を取ることが非常に困難です。
今回は運よく、H9年当時のカルテが廃棄されていたが、PCに氏名・初診日等の記録が有ったため、受診状況等証明書の⑩欄に「2」(受付簿より記載)に○印をして頂きました。
受診状況等証明書が整備出来た事
一番最初の医療機関では、氏名、診療科名、初診日のみの場合、2番目の医療機関で受診状況等証明書を作成しなければなりません。
近医からの紹介で受診した事と、発病から初診までの経過を丁寧に書いて頂いた事が初診日認定につながりました。
多数の事例がございますので、お気軽にお問い合わせください。
障害年金請求に関する腎疾患障害の特徴
初診日の特定が困難!
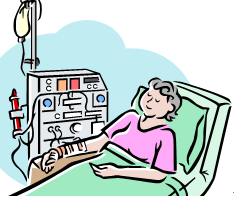
この病気の特徴は、10年~20年かけてゆっくりと進行し、最終的に慢性腎不全に移行することです。
障害年金の請求は、初診日が特定できないと請求できません。
健康診断等で最初に受診した医療機関名及び受診実施日を必ず記録しておくことが肝要です。
経過としては、多少の個人差がありますが発症時は有給休暇をとり、休職(1カ月~数年)を経て復職又は退職という経過をたどります。復職されてもまた発症し休職及び退職していく過程をたどっていくようです。
又病状は、糖尿病から慢性腎不全に移行し、最終的には人工透析療法(1回3~4時間、週3回)を受けられる傾向にあります。
障害認定日に特例あり!
人工透析の障害認定日は、初診日から1年6月以内の場合、人工透析を開始した日から3ヶ月が経過した日です。
尚1年6ヶ月を経過後に人工透析を開始した時は、3ヶ月が経過しなくても、事後重症請求や額改定請求が直ぐに出来ます。
従って、初診日から1年6ケ月以内に人工透析を開始した場合1年6ケ月を待たなくても、障害年金の請求が出来ますので、医師から病状を告げられたら直ぐに、請求の準備をされるとよいでしょう。
障害等級2級以上がほとんどです!
人工透析の該当等級は2級以上となっております。ですから初診日の時にサラリーマンや公務員である場合は、「障害基礎年金2級以上+障害厚生年金2級以上」の両方受給出来ます。
尚かつ障害年金の請求時に奥様や高校生のお子様がいる場合は、「子の人数分加算」と「配偶者加算」が加算されます。
障害年金が、非常に多く受給できます。
被保険者期間:300月みなし適用!
障害厚生年金の計算では、例えば23歳で入社し43歳で透析を開始後、認定を受けた場合でも、被保険者期間が20年(240月)ではなく、25年(300月)とみなして計算されます。
※被保険者期間が300月未満の場合は、300月とみなす特例があります。
従って45歳よりも若くして人工透析を開始された場合でも特例によって、生活費が
支えられる仕組みになっています。
事後重症請求の方が多い!

当事務所のお客様では、人工透析の方が沢山いらっしゃいます。
まだまだ事例がございますので、お気軽にお問い合わせください。
腎疾患の障害等級認定基準
腎疾患による障害の認定基準が一部改正しました。

平成27年6月1日より、腎疾患による障害の認定基準が一部改正されました。
認定に用いる検査項目を病態別に分け、項目の追加をしました。
また、判断基準を明確にするなどの見直しを行いました。
| 障害の程度 | 障 害 の 状 態 |
| 1 級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、おおむねベッドでの生活程度以上と認められる状態であって、日常生活がほとんど寝たきりの程度のもの |
| 2 級 | 身体の機能の障害が、必ずしも家族の助けを借りる必要はないが、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの |
| 3 級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
■腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとします。
当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とします。
1級 ⇒ 長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が家族の援助なしでは出来ない 程度(寝た切り状態)のもの
2級 ⇒ 日常生活が一部家族の援助なしでは出来ない又は日常生活に著しい制限を加える ことを必要とする程度のもの
3級 ⇒ 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。

(改正:平成27年6月1日より)
■ 認定要領
(1) 腎疾患による障害の認定の対象はそのほとんどが、慢性腎不全に対する認定である。
慢性腎不全とは、慢性腎疾患によって腎機能障害が持続的に徐々に進行し、生体が正常に維持できなくなった状態をいう。
すべての腎疾患は、長期に経過すれば腎不全に至る可能性がある。
腎疾患で最も多いものは、糖尿病性腎症、慢性腎炎(ネフローゼ症候群を含む。)、腎硬化症であるが、他にも、多発性嚢胞腎、急速進行性腎炎、腎盂腎炎、膠原病、アミロイドーシス等がある。
(2)腎疾患の主要症状としては、悪心、嘔吐、食欲不振、頭痛等の自覚症状、浮腫、貧血、アシドーシス等の他覚所見がある。
(3) 検査としては、尿検査、血球算定検査、血液生化学検査(血清尿素窒素、血清クレアチニン、血清電解質等)、動脈血ガス分析、腎生検等がある。
(4)病態別に検査項目及び異常値の一部を示すと次のとおりである。
① 慢性腎不全
| 区分 | 検査項目 | 単位 | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 |
| ア | 内因性クレアチニンクリアランス | ml/分 | 20以上30未満 | 10以上20未満 | 10未満 |
| イ | 血清クレアチニン | mg/dl | 3以上5未満 | 5以上8未満 | 8以上 |
注意:eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニンの異常に替えて、eGFR(単位はml/分/1.73㎡)が、10以上20未満のときは、軽度異常、10未満のときは、中等度異常と取り扱うことも可能です。
② ネフローゼ症候群
| 区分 | 検査項目 | 単位 | 異常 |
|
ア | 尿蛋白量 (1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比) | g/日 又は g/gCr | 3.5以上を 維持する |
| イ | 血清アルブミン(BCG法) | g/dl | 3.0以下 |
| ウ | 血清総蛋白 | g/dl | 6.0以下 |
(5)腎疾患による障害の状態を一般状態区分表で表すと次のとおりです。
一般状態区分表
| 区 分 | 一般状態 |
| ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふる まえるもの |
| イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は できるもの。例えば、軽い家事、事務など |
| ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
| エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中 の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
| オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
(6)各等級に相当する例示の中に、検査項目の異常の数を入れます
| 障害の程度 | 障 害 の 状 態 |
| 1級 | 前記(4)①(慢性腎不全)の検査成績が、高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
| 2級 | 1. 前記(4)①(慢性腎不全)の検査成績が、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
| 3級 | 1. 前記(4)①(慢性腎不全)の検査成績が、軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの 2. 前記(4)②(ネフローゼ症候群)の検査成績のうち、アが異常を示し、かつ、イ又はウのいずれかが、異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
(7) 人工透析療法施行中のものについては、原則として次により取り扱う。
ア. 人工透析療法施行中のものは2級と認定する。
なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
イ. 障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。
(8) 検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、腎疾患の経過中において最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて認定を行うものとする。
(9) 糸球体腎炎(ネフローゼ症候群を含む。)、腎硬化症、多発性嚢胞腎、腎盂腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係があるものと認められる。
(10) 腎疾患は、その原因疾患が多岐にわたり、それによって生じる臨床所見、検査所見も、また様々なので、前記(4)の検査成績によるほか、合併症の有無とその程度、他の一般検査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して総合的に認定する。
(11) 腎臓移植の取扱い
ア. 腎臓移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定する。
イ. 障害年金を支給されている者が腎臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は、従前の等級とする。
医療関係の皆様方へ
あきらめないで、障害年金受給しましょう!

障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非無料相談をご利用ください。
ごあいさつ
資格
- 2010年 社会保険労務士資格取得
- 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
- 2014年 特定社会保険労務士付記
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。



